事例264
コンじるで信じる!?情報のデジタル化の本質を考える
近江兄弟社高校 長谷川友彦先生

本日のテーマは「情報のデジタル化」です。
情報のデジタル化というと、2003年にちょうど教科「情報」が始まった当初から、様々実践されてきましたが、本日は、あらためて情報のデジタル化の本質が一体どこにあるのかということを考え、そして私がどのように授業を組み立ててきたかについて紹介したいと思います。
情報のデジタル化の本質
それでは、まず情報のデジタル化の本質がどこにあるのかを考えてみましょう。
それは情報というものをデジタル、すなわち数値に置き換えて表すというところにあると思います。
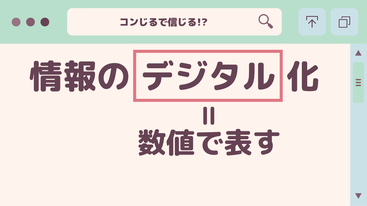
こちらは 、私の授業で使っている教材ですが、このように図形と数値を対応させることで、さまざまな図形を、数値を使って表すことができます。これがすなわち「情報というものをデジタルで表す」ということの意味なのです。

コンピュータ(computer)は、もともとコンピュート(compute)するもの、つまり「数値の計算をする道具」として登場しました。そして、情報を数値で表すことができれば、コンピュータというもので情報を扱うことができるようになるのです。つまり、「計算の道具」として登場したコンピュータが、「情報を扱う道具」へと進化してきた、というわけです。


デジタル情報の演算処理
さて、情報が数値で置き換えられ、コンピュータで扱うことができる、ということは何を意味するのでしょうか。
ここに情報のデジタル化の本質が隠されているように思うのです。
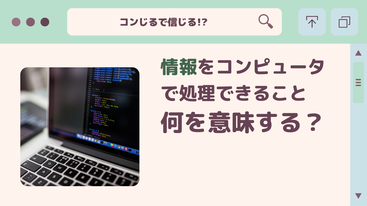
それは、情報が数値で表されているということから、情報を演算によって加工することができるということなんですね。

そこで私の授業では、情報が演算によって加工される例として、画像の加工を取り上げることにしました。画像を加工する例として「トーンカーブ」、それから「レベル補正」というものを扱いました。
では、こちらをご覧ください。
【トーンカーブ、レベル補正】https://youtu.be/C_i2c4wULls?t=153
これらの画像加工の手法は、いずれも画像の色の数値を変換することによって加工ができたわけです。
つまり、情報が数値によって表されているからこそ行えることなのです。


情報のデジタル化を体験し、プログラミングにつなげる
ここでもう一つ、このようなものを体験してもらおうと思います。
【コンじる】https://youtu.be/C_i2c4wULls?t=382
このような画像の加工を通して言えることは、写真というものは、もはや「撮る」ものではなく、「作る」ものだということなのです。現在、生徒たちも自分の姿を加工することで「盛る」ということをよく行っているわけですが、作られた写真というものをどう見るのか、どう読み解いていくのかということも、現代に生きる生徒たち全員に考えてもらいたいテーマの一つだと思っています。
この回の授業の生徒たちのコメントを見ていても、「画像が、いとも簡単に加工されてしまうというのを見て、何が本当なのかわからなくなり、怖くなった」というコメントがたくさん寄せられていました。
このように、情報のデジタル化というのは、情報が数値によって表されているために、演算によって容易に加工ができる、というところに本質があると思うのです。そのことを体験した上で、「それでは実際にどのように加工をしているのかということを知るために、次はプログラミングをやっていきましょう」と、本日ご紹介した情報のデジタル化の授業を、プログラミングの授業への導入としても扱っています。
ぜひ、何かの参考にしていただけると幸いです。
皆さんの中にも、「Photoshopなんて高くて買えへんわ」という方もいらっしゃるかと思います。本校でも、今年度の1年生からは1人1台端末として、全員がChromebookを持っていますので、Photoshopを使えるわけではありません。
そこで、同様のことができるWebサービスのPhotopea(※)というアプリをご紹介します。トーンカーブで明るさを調整したり、あるいはレベル補正で明るさの補正をしたりすることができます。もちろん「コンじる(コンテンツに応じる)」も、このPhotopeaで行うことができます。一度お使いになってみてください。
神奈川県情報部会実践事例報告会 2022 オンライン オンデマンド発表より












